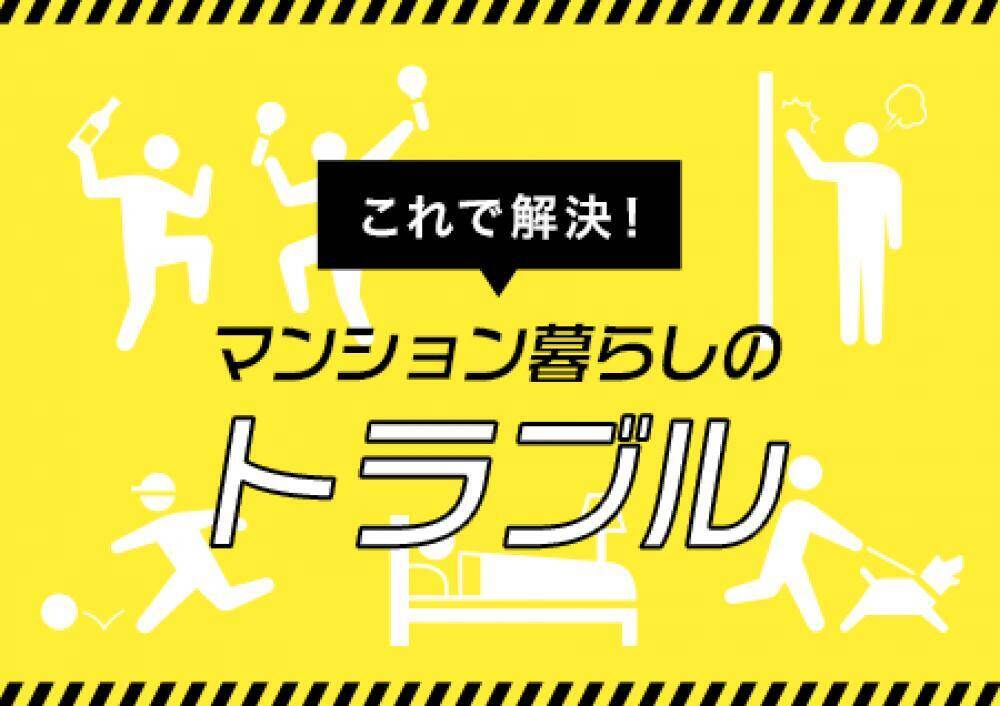マンションでよくある困った問題をテーマに、その解決方法を紹介していくこの連載。今回は「住宅ローン」のトラブルに目を向けたいと思います。
人生において最も大きな買い物のひとつであるマイホーム。分譲マンションの購入であっても、多くの人がローンを組んで取得するのではないでしょうか。
しかし、「思ったよりも返済がきつい」「金利が上がって返済額が増えた」といったトラブルもあります。
そこで今回は、住宅ローンにまつわるトラブルとその対処法について紹介します。
住宅ローンに関するトラブル

住宅ローンを契約してマンションを購入した場合、どんなトラブルが想定されるでしょうか。
【トラブル1】毎月の返済がきつい
毎月の住宅ローンの返済額を家賃と同程度の水準で設定してしまうと、家計を圧迫してしまう可能性があります。
住居を購入すると、住宅ローンの返済のほか修繕積立金や固定資産税などがかかってきます。数年経てば劣化してしまう家財もあるため、買い換え費用を準備しておく必要もあるでしょう。
また、返済スケジュールが定年後も続いていたり、ボーナスに頼りすぎたりすると、返済が滞ってしまう可能性もあります。
病気やケガ、失業や転職など、収入が減った場合に対応するため、もしもの時に備えた費用を手元に残こせるよう計画しておかなくてはなりません。
【トラブル2】金利が上がった

住宅ローン商品には、固定金利型と変動金利型があります。全期間固定金利の「フラット35」のような商品もあれば、3年、5年、10年など一定期間は固定金利となり、その後はいずれかを選択できる「固定金利期間選択型」の商品もあります。
変動金利型は半年に1度適用金利が改定され、返済額は5年に1度調整されます。変動金利を選んだ場合、初めは低金利で借りられていたものが、徐々に金利が上がった結果、返済額が多くなってしまう可能性があります。
【トラブル3】節税の手続きをしていなかった
「住宅ローン控除」は、ローンの返済期間が10年以上で専有面積が50㎡以上、所得税の控除を受ける年の合計所得が3000万円以下などの条件に当てはまる場合に所得税を減税できる制度です。
控除額は借入額や住宅の種類(「認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」かどうか)でも変わりますが、13年間毎年の住宅ローン残高の1%が所得税から控除されます(上限あり)。
注意したいのが、入居した翌年の3月15日までに確定申告をしないと控除が適用されないという点。2年目以降は年末調整で手続きができるので、初年度の申告を忘れずに行う必要があります。
自治体が実施している助成金の申請期限や条件も確認して申し込まなければ、節税のチャンスを逃してしまいます。
トラブルへの対処法
住宅ローンの問題は複雑で、自分で調べただけでは対処法がわからない場合もあるでしょう。すでに住宅ローンを契約している人は、借り換えを検討したい場合もあるかもしれません。そんなときの相談先を紹介します。
【対処法1】金融機関や不動産会社の無料相談を活用する

各金融機関や不動産会社では、住宅ローンの相談会を無料で行っています。
金融機関の相談会であればその場で審査の申し込みできる場合もあり、不動産会社の相談会であれば物件を含めた相談も可能です。
ただし、取り扱っている商品しか紹介できないうえ、個別のライフプランに合わせた商品を提示してくれるとは限りません。ある程度自分の家計や人生設計をイメージしてから相談に行くとよいでしょう。
【対処法2】FPに相談する
ファイナンシャル・プランナー(FP)は、人生における資産設計を手助けしてくれます。ランニングコストも含めた住宅資金や、子どもの教育費や老後の生活費も含めて家計管理のアドバイスを受けられます。
ただし、どのFPも住宅ローンに詳しいわけではないため、具体的な商品説明よりも返済プランや固定金利型と変動金利型の違いなどを把握するために活用するのがよいでしょう。
金融機関や不動産会社、保険会社に所属するFPだと、取り扱っている商品の紹介のみとなってしまうケースもあります。
企業に所属していない独立系FPなら、相談自体に費用がかかる代わりに、中立的な立場からアドバイスを受けられます。費用は、5000円から1万円程度としているところが多いようです。
【対処法3】税理士に相談する
住宅ローン控除や適用される優遇措置、助成金などは、税理士に相談するのもひとつの方法です。
もちろん、自分で情報収集をして申請をすることも可能です。住宅ローン控除の申請方法は国土交通省のウェブサイトでも確認できます。書類の取り寄せや、その他の助成金についてはお住まいの自治体の情報を確認してみてください。
税理士に相談した場合、1万円〜数万円程度の相談料がかかりますが、それでも忙しい人や必要書類の準備などを任せたい人はプロに相談するとスムーズでしょう。
以上、今回は住宅ローンに関するトラブルと、その対処法を紹介しました。
人生の大きな買い物に関わるからこそ重要で複雑な住宅ローンの問題。トラブルが起きる前にライフプランや家計にあった商品を選ぶ必要があります。すでに契約をしている人は、今のプランで滞りなく返済するために家計を見直したり、商品の借り換えを検討したりしてもよいでしょう。
自分で情報収集するのが難しい場合は、金融機関や不動産会社の無料相談も活用しながら、FPや税理士に相談することも考えてみてはいかがでしょうか。
イラスト:カワグチマサミ