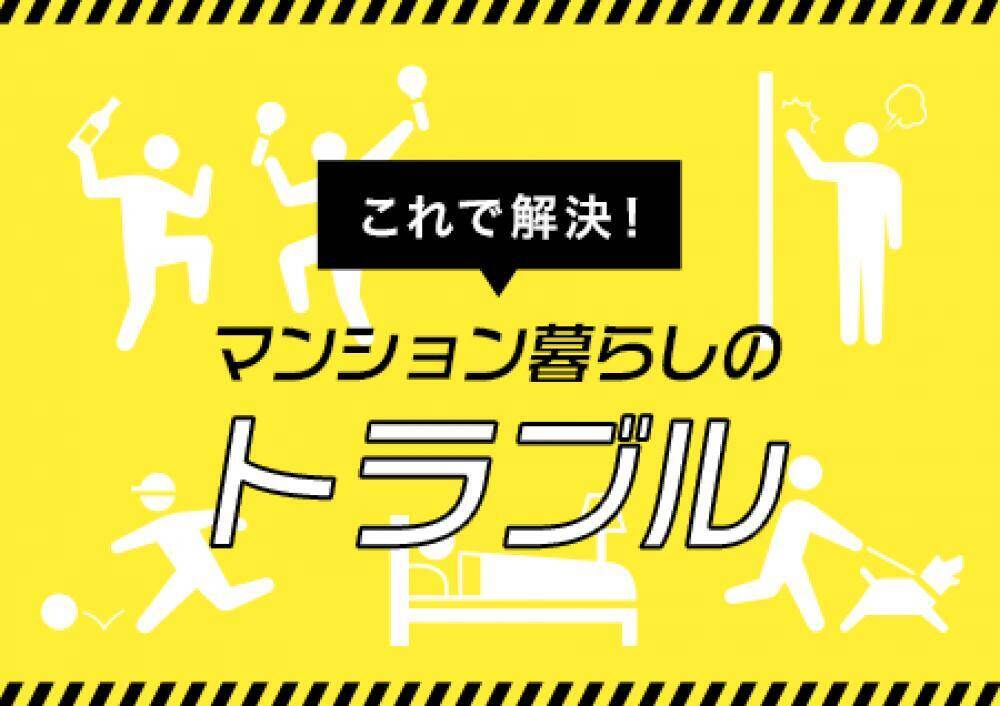マンションでよくある困った問題をテーマに、その解決方法を紹介していくこの連載。今回は、冬場に多くの家庭を悩ませる「窓の結露」に目を向けたいと思います。
冬の朝、窓ガラスが濡れている光景は、冬の風物詩のように思われがちです。しかし、この結露を放置すると、見た目の不快さだけでなく、カビの発生による健康被害や、家の内装を傷める原因にもなりかねません。特に気密性の高い現代のマンションでは、結露は深刻な問題に発展しやすい傾向があります。
そこで今回は、窓の結露が引き起こすトラブルとそのメカニズム、そして今日からできる具体的な対策について詳しく紹介します。
結露が引き起こす深刻なトラブル

結露を「ただの水滴」「いずれ乾くから放置でいいや」と侮ってはいけません。結露を放置することで、住まいと家族の健康にさまざまな悪影響が及ぶ可能性があります。
【トラブル1】カビの発生と健康被害
結露によって常に湿った状態が続くと、窓枠のパッキンやカーテン、壁紙などに黒カビが発生しやすくなります。カビは見た目が不衛生なだけでなく、その胞子を空気中に飛散させます。
このカビの胞子を吸い込むことで、アレルギー性鼻炎や気管支喘息、アトピー性皮膚炎、シックビル・シックハウス症候群などを引き起こしたり、症状を悪化させたりする原因になることが指摘されています。特に、免疫力の低い小さなお子様や高齢者がいるご家庭では、深刻な健康被害につながるリスクがあるため注意が必要です。
【トラブル2】内装材の劣化と建物の損傷
結露から流れ落ちた水分は、窓枠やその周辺の建材にダメージを与えます。木製の窓枠は水分を吸収して腐食したり、塗装が剥がれたりします。
さらに水分が壁紙に染み込むと、接着剤が劣化して剥がれや変色の原因になります。壁の内部にまで湿気が及ぶと、石膏ボードがもろくなったり、断熱材が湿って性能が低下したりすることも。フローリングにまで水分が達すれば、シミや床材の反り、腐食につながる可能性もあり、修繕には高額な費用がかかるケースも少なくありません。
【トラブル3】断熱性の低下と光熱費の増加
窓は家のなかで最も熱が出入りしやすい場所です。窓ガラスにびっしりと結露が付いている状態は、窓の断熱性能が著しく低下しているサインです。
窓から室内の暖かい空気が逃げやすくなるため、暖房を付けても部屋がなかなか暖まりません。結果として、暖房の設定温度を上げたり、運転時間を長くしたりすることになり、冬場の光熱費が余計にかさんでしまうのです。結露対策は、快適な室温を保ち、省エネにつなげるためにも重要です。
なぜ結露は発生するのか? マンション特有の事情
結露対策を効果的に行うためには、まずその発生メカニズムを理解することが大切です。
結露は、「高い湿度」と「室内外の温度差」という2つの条件が揃ったときに発生します。
空気中には水蒸気として水分が含まれていますが、空気が含むことのできる水蒸気の量は、温度によって決まっています。暖かい空気ほど多くの水蒸気を含むことができ、冷たい空気は少ししか含むことができません。
冬場、暖房で暖められた室内の空気は、多くの水蒸気を含んでいます。この湿った空気が、外気で冷やされた窓ガラスやサッシに触れると、急激に冷やされます。空気の温度が下がると、含みきれなくなった水蒸気が水滴に変わり、窓に付着します。これが結露の正体です。冷たい飲み物を入れたコップの表面に水滴がつくのと同じ原理です。
特に、近年のマンションは結露が発生しやすい環境といえます。コンクリート造のマンションは、木造住宅に比べて気密性が非常に高く、隙間風が入りにくい構造です。これは冷暖房効率が良いというメリットがある一方、室内の湿気が外に排出されにくく、こもりやすいというデメリットにもなります。
また、洗濯物の室内干し、加湿器の使用など、現代の生活は室内の湿度を上げる要因が多くあります。気密性の高いマンションでこうした生活を送ることで、結露のリスクはさらに高まります。
結露への具体的な対処法
【対処法1】基本は「換気」。24時間換気システムを止めない

最も重要かつ効果的な対策は「換気」です。室内にこもった湿った空気を、外の乾いた空気と入れ替えることで、結露の発生を根本から抑えることができます。
2003年以降に建てられたマンションには、24時間換気システムの設置が義務付けられています。電気代がもったいない、冬場は寒いといった理由で止めてしまう方もいますが、24時間作動させておくことをおすすめします。このシステムは、室内の空気を常に少しずつ入れ替え、湿度や化学物質がこもるのを防ぐための重要な設備です。基本的に、常に運転させておきましょう。吸気口のフィルターが汚れていると換気効率が落ちるため、定期的な清掃も忘れずに行いましょう。
また、調理中や入浴後など、特に湿度が高くなるタイミングでは、窓を開けて集中的に換気するのが効果的です。冬場は、1回あたり5分~10分程度、2か所以上の窓を開けて空気の通り道を作ると、室温を大きく下げることなく効率的に空気を入れ替えられます。
【対処法2】湿度をコントロールする生活習慣
日々の暮らしのなかで少し意識するだけで室内の湿度を適切に保つことができるポイントがあります。
まず、室内干しは湿度を上げる大きな原因です。できるだけ浴室乾燥機や洗濯乾燥機を活用しましょう。それが難しい場合は、除湿器を併用したり、換気扇を回している浴室や脱衣所に干したりするのがおすすめです。リビングなど人が常にいる部屋に干すのは避けましょう。
また、乾燥対策で加湿器を使う際は、湿度計を設置し、室内の湿度が40〜60%になるように調整しましょう。過度な加湿は結露の直接的な原因となります。
【対処法3】手軽に始められる対策グッズを活用する
ホームセンターやインターネット通販では、結露対策に役立つさまざまなグッズが販売されています。
結露吸水テープは、窓の下部に貼り、流れ落ちる水滴を吸収するテープです。カビの発生を抑える効果があるものもありますが、吸収した水分を放置するとテープ自体がカビの原因になるため、こまめな交換が必要です。
窓に断熱効果のあるシートを貼ったり、撥水効果のあるスプレーを塗布したりすることで、結露の発生を抑制します。透明なタイプを選べば、外の景色を損なうこともありません。
窓際にサーキュレーターを置き、窓に向けて風を送ることで、窓周辺の空気のよどみをなくし、空気が冷やされるのを防ぎます。これにより結露の発生を抑える効果が期待できます。
室内の湿度を直接的に下げる最も強力な方法の一つが、除湿機の使用です。特に洗濯物を室内干しする際に併用すると、衣類が早く乾くだけでなく、住戸全体の湿度上昇を効果的に防げます。また、クローゼットや押し入れ、靴箱など、空気の流れが滞りやすい場所には、置き型の除湿剤を設置するのも効果的です。
【対処法4】根本解決を目指すリフォーム
結露をより根本的に解決したいという場合は、リフォームも有効な選択肢です。
内窓(二重窓)の設置は、既存の窓の内側にもう一つ窓を設置する方法です。既存の窓との間に空気層ができることで断熱性が飛躍的に向上し、外の冷気が室内に伝わりにくくなるため、結露を強力に抑制します。防音効果や防犯性能が高まるというメリットもあります。
複層ガラス(ペアガラス)への交換という、窓のガラスを、2枚のガラスの間に空気層や特殊なガスが封入された複層ガラスに交換する方法もあります。これも高い断熱効果があり、結露防止に有効です。
これらのリフォームは費用がかかりますが、光熱費の削減にもつながるため、長期的な視点で見れば経済的なメリットも期待できます。なお、窓はマンションの共用部分にあたる場合があるため、リフォームを行う際は事前に必ず管理規約を確認し、管理組合に相談・申請を行いましょう。
以上、今回は窓の結露に関するトラブルと、その対処法を紹介しました。
結露は単なる水滴ではなく、放置すればカビや建物の劣化につながる住まいの危険信号です。まずは日々の換気や湿度管理を徹底することから始め、必要に応じて便利なグッズやリフォームも検討してみてください。適切な対策で、冬の住まいを快適かつ健康的に保ちましょう。
イラスト:カワグチマサミ