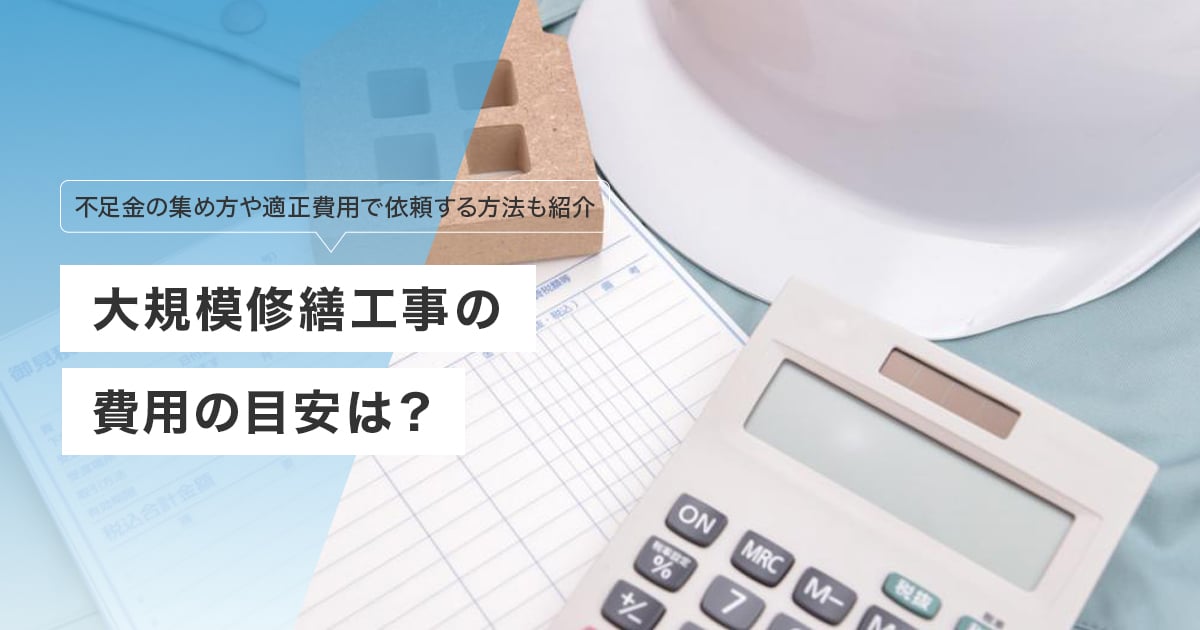マンションの大規模修繕といえば「12〜15年周期」が一般的とされてきましたが、近年注目を集めているのが「16〜18年」といった長めの周期で修繕を行う「ロングスパン化」です。修繕の周期を長くとり、工事の回数を減らすため、結果的に工事費用を抑制につながります。
ロングスパン修繕を成功させるには、適切な診断や資材選定、そして定期的なメンテナンスが欠かせません。
そこでおすすめなのが、無料で修繕費用の目安を把握できる「大規模修繕シミュレーター」の活用です。実際の施工実績にもとづいたシミュレーションにより、信頼性の高いコスト試算が可能となっています。また、豊富な実績も公開されているため、自分たちのマンションに近いケースを参考にしながらの計画が可能です。。
この記事では、ロングスパンの大規模修繕の具体的なメリットと、失敗しないためのポイントをわかりやすく解説します。将来にわたり安心・快適な住環境を維持したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
ロングスパンサイクルの大規模修繕とは

マンションの資産価値を保ち、住環境を快適に維持するためには、定期的な修繕が欠かせません。そのなかでも「大規模修繕工事」は、工事規模・費用・期間のいずれにおいても非常に大きなウェイトを占める重要な工事です。建物の外壁や共用部分、設備などの劣化に対して、計画的かつ集中的に手を入れ、長期的な安全性や美観、快適性を確保します。
これまで多くのマンションでは、概ね12~15年ごとに大規模修繕を行うのが一般的でした。実際、国土交通省が令和3年度に実施した調査によると、大規模修繕の実施周期として最も多いのは「13年」であり、それ以外も「12年」「14年」「15年」と続いており、全体のおよそ7割がこの12~15年の範囲内で修繕を行っています。
しかし近年では、こうした従来の周期を見直し、16~18年の長いスパンで大規模修繕を計画・実施する「ロングスパンサイクル」の考え方が注目されています。例えば、新築から50年間という期間で比較した場合、12年ごとの修繕では計4回の工事が必要になりますが、16年周期では3回、18年周期ではわずか2回に抑えられます。これにより、長期的な視点では工事回数の削減によるコスト低減が期待できるでしょう。
このようなロングスパン化を実現するためには、修繕工事に用いる材料や工法の見直しが不可欠です。例えば、耐久性に優れた「長寿命化材料」を採用すると、劣化の進行を抑えられるため、次回の修繕時期を大幅に先送りできる可能性があります。
ロングスパンサイクルで行う大規模修繕3つのメリット
ロングスパンサイクルで実施する大規模修繕には、大規模修繕費用の削減やマンションの資産価値向上、管理組合・理事会の労力が軽減などのメリットがあります。それでは、各メリットについて詳しく見ていきましょう。
【メリット1】大規模修繕費用が削減できる

マンションの大規模修繕には多くの費用が必要になりますが、修繕周期を延ばすと工事の回数を減らせるため、結果として全体のコストの抑制につながります。
ロングスパン化導入のために耐久性に優れた建材や劣化しにくい工法を取り入れる場合、1回あたりの工事費用はやや高額になる場合もあります。しかし、それでも修繕の頻度自体が減るため、結果的にコストパフォーマンスはむしろいいと感じられるケースも多いようです。
また、工事はそのたびに足場の設置費用や管理経費などの付帯コストがかかってきます。特に仮設足場は他の用途に流用できませんので、工事回数を減らした分だけこのようなコストを抑えられます。
以上の理由により、修繕周期を長く設定すると、修繕積立金に余裕が生まれる可能性があります。その分を日常的な小規模修繕や、次回の大規模修繕に充てられたり、余裕を持った資金計画を立てやすくなるでしょう。

大規模修繕の無料見積もりはこちら
大規模修繕費用の簡易見積へ【メリット2】マンションの資産価値が向上する

最新の材料や技術を取り入れた修繕工事を行えば、それだけ建物全体の高耐久化が可能です。
例えば塗装ひとつをとっても、使用する塗料によって耐用年数に大きな違いがあります。シリコン樹脂の塗料は期待耐用年数が10年程度、メーカーの保証期間が5年程度となっているのが一般的ですが、フッ素樹脂の塗料であれば期待耐用年数は15〜20年、保証期間が10年程度と長期間にわたり劣化を防げるため、修繕の頻度の抑制が可能です。
こうした取り組みは、建物の構造的な健全性だけでなく、美観の維持にもつながります。外壁のひび割れや色あせの目立たない状態を保つことは、居住者の満足度向上に貢献するだけでなく、外部からの印象にも好影響を与えるでしょう。
さらに、質の高い材料や工法による修繕実績があると、将来的に物件を売却する際の評価にもつながりやすいです。丁寧にメンテナンスされてきたマンションは、中古市場でも好印象を与えやすいため、リセールバリューの向上に期待ができます。
高耐久な仕様にすると工事費用は一時的に増える場合がありますが、長期的に見れば投資価値の高い修繕となるといえます。
【メリット3】管理組合・理事会の労力が軽減できる
大規模修繕工事では、通常、修繕委員会が中心となって準備や進行管理を行いますが、管理組合や理事会にも多くの役割が求められます。
工事内容の確認や住民からの問い合わせ対応、定例会への出席、進捗状況の把握、情報発信、資金面の調整など、その範囲は幅広く、負担は決して軽くありません。修繕方式や規模によって変わりますが、検討事項や意思決定、関係者との調整が多いため、工事予定の概ね1年前から本格的に準備を始めるべきでしょう。
このように長期間にわたる準備と細やかな対応が必要不可欠な大規模修繕工事は、管理組合や理事会の負担も大きいのが実情です。しかし、修繕の周期を延ばしてロングスパン化すると、工事に関わる回数自体が減るため、理事会の業務負担の軽減ができます。その分、日常の管理業務や住民サービス、将来の計画にリソースを割きやすくなり、マンション全体の運営効率向上に寄与できます。
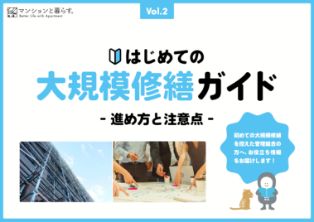
大規模修繕の進め方をまとめました
資料ダウンロードはこちらロングスパンの大規模修繕を成功させる3つのポイント
ロングスパンでの大規模修繕を効果的に進めるには、事前の準備や継続的な管理が不可欠です。ここでは、実施にあたって特に意識すべき3つのポイントを順にご紹介します。
【ポイント1】建物診断を実施し業者や専門家の判断を仰ぐ
ロングスパンでの大規模修繕を検討する際、まず欠かせないのが建物診断の実施です。修繕の周期を延ばすと多くのメリットがありますが、前提として建物の状態を正確に把握し、適切に対応している必要があります。
例えば、外壁にひび割れやタイルの欠損が見られる場合、放置すれば劣化は目に見えない部分にまで進行し、将来的に大きな補修が必要になる可能性があります。修繕時期の先延ばしがかえってコスト増につながるケースもあるため、慎重な判断が必要です。
そのためにも、経験豊富な専門家や施工業者に相談したうえでの、客観的な診断結果を踏まえた判断が重要です。調査・診断の結果から、どの程度の傷みがあり、今すぐ対応すべきか、あるいは多少の先延ばしが可能かといった判断が可能になります。
使用する材料の選定や工法についても、専門家の助言を受けながら進めれば、より的確な長期修繕戦略が可能になります。建物の資産価値を守り、長く安心して暮らせる環境を維持するためにも、まずは信頼できる専門家と連携し、現状をしっかりと見極めるところから始めましょう。
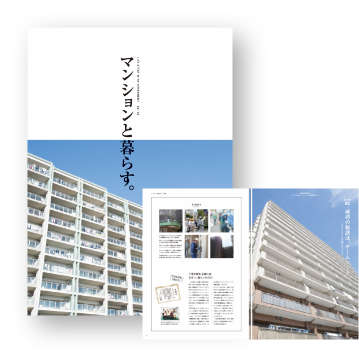
カシワバラ・コーポレーションの修繕実績
資料ダウンロードはこちら【ポイント2】1回あたりの工事費用は割高になる可能性を念頭に置いて計画を立てる
前述の通り、ロングスパン化した大規模修繕では、耐久性の高い建材や工法を採用する必要があるため、1回あたりの工事費用は割高になる傾向があります。
長期的にはコスト削減につながる可能性がありますが、初期費用が増える点は念頭に置いておく必要があります。
さらに、資材価格の高騰や追加工事の発生リスクも考慮しなければなりません。例として、外壁に高耐候なフッ素塗料を使用した場合、次回の塗装時には付着性を高めるための処理が必要になり、別途費用がかかる場合もあります。
修繕積立金だけでは費用をまかなえない可能性もあるため、支出の優先順位や修繕内容の見極めが重要です。「今、本当に必要な工事なのか」「標準的な仕様で十分なのか」「グレードを上げるべきか」といった点について、専門家と相談しながらの慎重な判断が求められます。
【ポイント3】定期的な点検とメンテナンスを実施する
ロングスパンで大規模修繕を計画する場合でも、その間ずっと何もしなくてよいわけではありません。次回の修繕までの期間中も、定期的な点検と必要に応じたメンテナンスが不可欠です。
まず、大規模修繕工事にはアフターサービスがあり、各工事にはそれぞれ保証期間が設定されています。工事完了後に不具合が見つかった場合でも、その保証により修繕対応が可能な場合があります。内容や期間は施工会社によって異なるため、事前に確認をしておきましょう。
さらに、分譲会社が独自に実施するアフター点検もあります。一般的には、引き渡しから半年、1年、2年、5年など、一定のタイミングで実施され、不具合の有無をチェックする制度です。
こうした点検の結果をもとに、必要な補修を施工業者と相談しながら適切に進めていくという取り組みが、建物の劣化抑制につながります。
定期点検と信頼できる業者選びがロングスパン修繕成功のカギ
従来の12〜15年周期よりも長い16〜18年周期で行うロングスパンの大規模修繕には、工事回数の削減や管理組合・理事会の負担軽減、環境負荷の抑制といったさまざまな利点があります。1回あたりの工事費用は高額になる可能性があるものの、回数の削減によりトータルのコストを抑えられるケースも多いです。
ただし、こうした長周期の修繕計画を成功させるためには、建物の劣化状況の正確な把握が欠かせません。専門家の診断を受けたうえで、判断する必要があります。
また、長期間にわたり建物の性能を保つためには、工事と工事の間にも定期的な点検や軽微な補修を行うなどして、劣化の進行抑制に取り組む必要があります。アフターサービスの活用といった、建物の状態を継続的に確認する働きが、修繕のコスト効率向上のカギです。
ロングスパン修繕は、単に周期を延ばすという選択ではなく、建物の長寿命化と資産価値の維持を目指すための一つの手段です。中長期的な視点に立って、信頼できる業者とともに計画的に取り組む姿勢が何よりも重要です。

大規模修繕の無料見積もりはこちら
大規模修繕費用の簡易見積へ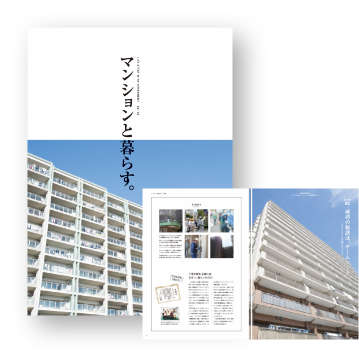
カシワバラ・コーポレーションの修繕実績
資料ダウンロードはこちら