
目次
28歳で福岡へ移住し、築40年の物件をセルフリノベーションしながら生活。その様子をブログメディア「DIY MAGAZINE」で公開しているセーチです。2軒目3軒目4軒目に続いて、福井県にある旧耐震空き家を新耐震にフルリノベーションする過程をお届けします。
福井県の旧耐震空き家をリノベーション

via
diy-magazine.jp
こんにちは。祖父母の物件をセルフリノベーションしつつ、インテリアなどを作っているセーチです。
福井県の築55年になる旧耐震空き家。
1級建築士の元、旧耐震の空き家を新耐震に工事し、空き家を購入して活用したいと思う方々の参考になるようリノベーションしていきます。
前回は解体作業をし、ほぼほぼスケルトン状態までもっていきました。今回は1級建築士の先生と耐震調査して補強プランを練る作業です。
福井県の築55年になる旧耐震空き家。
1級建築士の元、旧耐震の空き家を新耐震に工事し、空き家を購入して活用したいと思う方々の参考になるようリノベーションしていきます。
前回は解体作業をし、ほぼほぼスケルトン状態までもっていきました。今回は1級建築士の先生と耐震調査して補強プランを練る作業です。
解体後の状態を確認

via
diy-magazine.jp
2022年の2月の段階で仮の耐震補強プランを頂いていたので、1級建築士の先生が来る前に解体後の状態を観ながら一通り目を通しておきます。1階だけでなく2階も解体済みなので、筋交いの場所や耐震壁の場所を確認します。
図面を見ながら打ち合わせ

via
diy-magazine.jp
耐震プラン図面と耐震壁の数値について資料を頂きました。
筋交いをいれる場所と入れるかもしれない場所を想定し、合計数値が評点の1.00を超えるように図面に落としているそうです。
横向きがX方向、縦向きがY方向として、縦向き横向きの両方の強度が評点1.00を超えれば、耐震基準をクリアしたということになります。
筋交いをいれる場所と入れるかもしれない場所を想定し、合計数値が評点の1.00を超えるように図面に落としているそうです。
横向きがX方向、縦向きがY方向として、縦向き横向きの両方の強度が評点1.00を超えれば、耐震基準をクリアしたということになります。
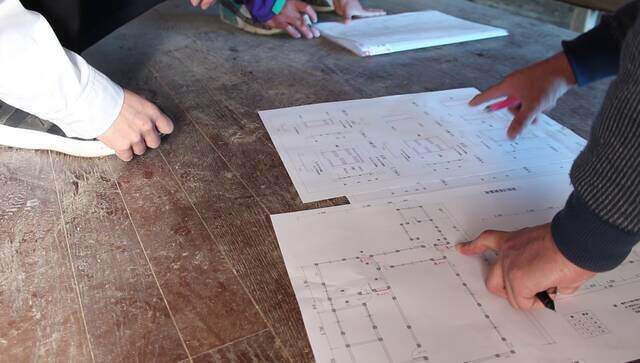
via
diy-magazine.jp
解体後、確認した筋交いや耐震壁の状況だと、まったく足りていないので、現状の筋交いが入っている場所にプラスして耐震壁を設置する場所を想定し、1.00の評点を超えるような補強プランにしています。
今回の事前確認で、筋交いを入れる場所や耐震壁にできる場所を確定させ、改めて耐震強度を再計算し、基準をクリアできるか後日判断します。
耐震壁とは別に耐力を確保する場所には合板を張って耐力壁にします。
耐力壁は張り方によって耐力が変わるので、指定の張り方を数値に落とした図面があります。
ざっくり簡単にまとめると、「大壁」と「真壁」の2種類があり、柱の外に合板を固定するか内に固定するかの違いです。
真壁は柱の内側に合板を固定する受けを取り付けて耐力壁にする方法で、柱の面(つら)に合わせて壁を作れるので壁がふけることなく収めることができます(出っ張らない)
今までの経験があるので、言っている意味が分かりますが何も知らない人が聞くと 「面材を打ってる」「受け材」「仕上げがふける」など、何言ってるのか分からないだろうなと思いました。
今回の事前確認で、筋交いを入れる場所や耐震壁にできる場所を確定させ、改めて耐震強度を再計算し、基準をクリアできるか後日判断します。
耐震壁とは別に耐力を確保する場所には合板を張って耐力壁にします。
耐力壁は張り方によって耐力が変わるので、指定の張り方を数値に落とした図面があります。
ざっくり簡単にまとめると、「大壁」と「真壁」の2種類があり、柱の外に合板を固定するか内に固定するかの違いです。
真壁は柱の内側に合板を固定する受けを取り付けて耐力壁にする方法で、柱の面(つら)に合わせて壁を作れるので壁がふけることなく収めることができます(出っ張らない)
今までの経験があるので、言っている意味が分かりますが何も知らない人が聞くと 「面材を打ってる」「受け材」「仕上げがふける」など、何言ってるのか分からないだろうなと思いました。

via
diy-magazine.jp
大壁は釘だけで柱に固定するので、釘の強度で支えているだけになり真壁に比べると耐力が劣ります。
真壁は柱の中にはめ込む形なので、合板の強度で支えることになり真壁の方が強度が強い計算になるそうです。
旧耐震の物件は、梁や柱や筋交いが金物で固定されていないので、強度的には約2割ほど落ちる計算になります。2割も耐震強度が落ちると、その分筋交いを追加したり耐震壁を取り付けないといけなくなるので金物の取り付けは必須です。
仕上がりの兼ね合いもあるので、真壁・大壁の判断は大工さんにしてもらい、筋交いを入れれる箇所はなるべく入れたいと思っています。筋交いは「45mm × 90mm」 サイズで計算しますが、一部30×90サイズがあったのでその分強度は下がります。(現在取り付けられている筋交いが若干細いようです)
真壁は柱の中にはめ込む形なので、合板の強度で支えることになり真壁の方が強度が強い計算になるそうです。
旧耐震の物件は、梁や柱や筋交いが金物で固定されていないので、強度的には約2割ほど落ちる計算になります。2割も耐震強度が落ちると、その分筋交いを追加したり耐震壁を取り付けないといけなくなるので金物の取り付けは必須です。
仕上がりの兼ね合いもあるので、真壁・大壁の判断は大工さんにしてもらい、筋交いを入れれる箇所はなるべく入れたいと思っています。筋交いは「45mm × 90mm」 サイズで計算しますが、一部30×90サイズがあったのでその分強度は下がります。(現在取り付けられている筋交いが若干細いようです)

via
diy-magazine.jp
想定していた箇所に筋交いがなく驚いている先生。
現状より少しでも数値が落ちるとアウトなので、合板の耐力壁を追加することになりました。
もともとキッチンがあった場所は片方しか筋交いが入っていいないので、壁を解体してタスキになるよう追加します。(ここで追加の解体作業を依頼します。)
洗面所の構造も確認。
トイレの背面にあった壁は筋交いが入っていなかったので、片筋だけとりつけることになりました。
1階はこれで終わり、2階も同じように確認します。
現状より少しでも数値が落ちるとアウトなので、合板の耐力壁を追加することになりました。
もともとキッチンがあった場所は片方しか筋交いが入っていいないので、壁を解体してタスキになるよう追加します。(ここで追加の解体作業を依頼します。)
洗面所の構造も確認。
トイレの背面にあった壁は筋交いが入っていなかったので、片筋だけとりつけることになりました。
1階はこれで終わり、2階も同じように確認します。

via
diy-magazine.jp
耐震調査が終わったので、解体で気になった1階の柱について確認をしました。
私が画像で触っている柱(床の間柱)は2階の梁を支える形になっているので、外してはダメな柱だそうです。その隣の柱も、取り付け方を見ると外さない方がいいそうなので、2本とも残すことになりました。(解体する前は、床の間の飾り柱と想定していましたが、まさか2階の梁を支えているとは思いませんでした。)
横の柱と画像右側の柱(リビング側)は外しても問題ないそうです。
一番気になっていたリビング側の柱は、既存の梁だけでは強度が足りないので補強が必須のようです。元ある梁に角材を添えるように正しい方法で追加すれば問題ないそうです。
私が画像で触っている柱(床の間柱)は2階の梁を支える形になっているので、外してはダメな柱だそうです。その隣の柱も、取り付け方を見ると外さない方がいいそうなので、2本とも残すことになりました。(解体する前は、床の間の飾り柱と想定していましたが、まさか2階の梁を支えているとは思いませんでした。)
横の柱と画像右側の柱(リビング側)は外しても問題ないそうです。
一番気になっていたリビング側の柱は、既存の梁だけでは強度が足りないので補強が必須のようです。元ある梁に角材を添えるように正しい方法で追加すれば問題ないそうです。

via
diy-magazine.jp
梁の補強は合わせ梁という方法をとります。
梁の下に1本太い角材を追加して合板で挟み込むように固定、そうすれば合わせ梁になり、一体物の梁として計算できます。追加する角材の固定は受金物が合うなら金物で固定でも良いそうです。(その方が安心)
ここら辺は大工さんと確認してもらいながら進めたいと思います。
床柱は2本残す形になったので、これでリビングキッチンの配置を考えなおします。
梁の下に1本太い角材を追加して合板で挟み込むように固定、そうすれば合わせ梁になり、一体物の梁として計算できます。追加する角材の固定は受金物が合うなら金物で固定でも良いそうです。(その方が安心)
ここら辺は大工さんと確認してもらいながら進めたいと思います。
床柱は2本残す形になったので、これでリビングキッチンの配置を考えなおします。
修正した耐震補強プランを大工さん含めて確認

via
diy-magazine.jp
後日、耐震補強で確定した箇所を再計算し、図面に落としてもらいました。
今回は大工さんも含め、耐震補強の足りなかった方向と施工方法の確認をしていきます。
既存の筋交いでも、切欠いている物は全部交換が必要とのことなので、かなりの数の筋交いを入れることになります。この打ち合わせ後に確定した図面を貰い、それに沿って耐震補強をおこないます。
筋交いは柱を固定する金物の指定もあるそうなので、どういった物を準備するか楽しみです。
※ここまでの作業風景を動画にまとめています。
今回は大工さんも含め、耐震補強の足りなかった方向と施工方法の確認をしていきます。
既存の筋交いでも、切欠いている物は全部交換が必要とのことなので、かなりの数の筋交いを入れることになります。この打ち合わせ後に確定した図面を貰い、それに沿って耐震補強をおこないます。
筋交いは柱を固定する金物の指定もあるそうなので、どういった物を準備するか楽しみです。
※ここまでの作業風景を動画にまとめています。
次回、床下のシロアリ対策や湿気対策を行ってから耐震施工に入っていきます。
このシリーズでは、旧耐震の空き家を新耐震に工事し、空き家を購入して活用したいと思う方々の参考になるよう、タグに「セーチの旧耐震リノベ」とつけているので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。ぜひ参考にしてくださいね。
このシリーズでは、旧耐震の空き家を新耐震に工事し、空き家を購入して活用したいと思う方々の参考になるよう、タグに「セーチの旧耐震リノベ」とつけているので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。ぜひ参考にしてくださいね。







