
目次
28歳で福岡へ移住し、築40年を超える2軒の物件をセルフリノベーションしながら生活。その様子をブログメディア「DIY MAGAZINE」で公開しているセーチです。前回、解体した床を貼り直す作業をしました。今回は床が今にも抜け落ちそうなボロボロ押入れの解体と床の貼り直し作業です。
セーチのDIYリノベ記録 一軒目
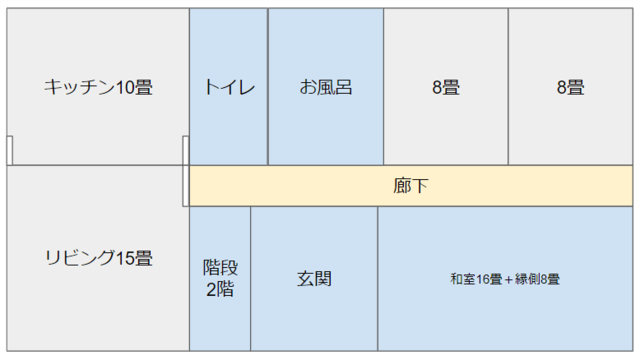
via
diy-magazine.jp
こんにちは。28歳で福岡へ移住し、築40年を超える2つの物件をセルフリノベーションしながら生活しているセーチです。
前回、和室と洋室の床を貼り直す作業をしました。
今回、壁の塗装作業に入ろうと思っていましたが、押入れの床が今にも抜け落ちそうな状態だったので、先に押入れの床を張替えてしまおうと思います。
前回、和室と洋室の床を貼り直す作業をしました。
今回、壁の塗装作業に入ろうと思っていましたが、押入れの床が今にも抜け落ちそうな状態だったので、先に押入れの床を張替えてしまおうと思います。
前回の記事はこちらから
解体前の状態

via
diy-magazine.jp
奥行き900mm、横幅3600mm。
上中下段に分かれている昔ながらの押入れです。
天袋は身長180㎝ある僕でも、手を伸ばしてギリギリ届くかどうかの高さです。
今回、部屋を完全に洋室化するので、押入れを一部解体して使いやすいようにDIYしようと考えています。
上中下段に分かれている昔ながらの押入れです。
天袋は身長180㎝ある僕でも、手を伸ばしてギリギリ届くかどうかの高さです。
今回、部屋を完全に洋室化するので、押入れを一部解体して使いやすいようにDIYしようと考えています。
押入れを解体

via
diy-magazine.jp
押入れの天板は、枠の上に置いてあるタイプが多く、バールで叩けば外れると思い解体し始めましたがビクともしませんでした。そのため、今回は丸ノコで切断します。
この時に気づきましたが、この押入れ、壁に埋め込まれている備え付けタイプでした・・・。
釘やビスで固定されている押入れと違って壁に埋め込まれているので、無理やり外そうとすると壁も一緒に崩れてしまうんです・・・。
この時に気づきましたが、この押入れ、壁に埋め込まれている備え付けタイプでした・・・。
釘やビスで固定されている押入れと違って壁に埋め込まれているので、無理やり外そうとすると壁も一緒に崩れてしまうんです・・・。

via
diy-magazine.jp
押入れの前面を解体すると天板が外れましたが、備え付けタイプだったので壁に天板の厚さ分だけ穴が開いています。
さらに、天板の土台の一部が隣の棚と繋がっていて、切断しないと解体できないことが分かりました。※先に切断した画像を見せます。
さらに、天板の土台の一部が隣の棚と繋がっていて、切断しないと解体できないことが分かりました。※先に切断した画像を見せます。

via
diy-magazine.jp
なかなか頑丈に作られていますね。
左側の押入れは、このまま使うので中段の板を解体する予定はありません。
なので、柱に沿って切断することにしました。
左側の押入れは、このまま使うので中段の板を解体する予定はありません。
なので、柱に沿って切断することにしました。

via
diy-magazine.jp
端だけ切断しても、頑丈でビクともしません。
丸ノコで細かく切れ目を入れてバールで解体します。
天板を乗せていた根太は、奥の板に釘止めされているので下からバールで打ち上げるように撤去。押入れ奥側の天板を支えていた板は、壁にガッチリ固定されているので上下に動かすと壁が崩れてしまいそうでした。そのため奥側の板はこのままにしておき、残りの木材だけを外すようにゆっくり作業を進めます。
丸ノコで細かく切れ目を入れてバールで解体します。
天板を乗せていた根太は、奥の板に釘止めされているので下からバールで打ち上げるように撤去。押入れ奥側の天板を支えていた板は、壁にガッチリ固定されているので上下に動かすと壁が崩れてしまいそうでした。そのため奥側の板はこのままにしておき、残りの木材だけを外すようにゆっくり作業を進めます。

via
diy-magazine.jp
徐々に打ち込み部分が緩んできましたが、やはりこの板も備え付けでした。隣の柱に釘で固定されているので切断することもできず、仕方なく壁の一部もろとも解体していきます。
そして外れると同時に、壁の板も緩んで取れてしまいました。
そして外れると同時に、壁の板も緩んで取れてしまいました。

via
diy-magazine.jp
板が外れた跡です。
押入れの壁は、竹の上に珪藻土か漆喰で固められている作りでした。
土や竹で作られている壁は、初めて見たのでビックリです。
備え付けの押入れでなければ、そのまま中段の板を解体して終了ですが、築40年の古い作りなので仕方ないですね。最終的にはパテで埋めて補修しようと思っています。
押入れの壁は、竹の上に珪藻土か漆喰で固められている作りでした。
土や竹で作られている壁は、初めて見たのでビックリです。
備え付けの押入れでなければ、そのまま中段の板を解体して終了ですが、築40年の古い作りなので仕方ないですね。最終的にはパテで埋めて補修しようと思っています。
押入れの床の様子

via
diy-magazine.jp
張替える前の押入れの床です。
見ただけで傷んでるのがわかります。
とても物を置ける状態ではなく、僕が上に乗ると簡単に穴が開きました。
特に痛みが激しい所は床がめくれて釘も浮いてしまっています。
見ただけで傷んでるのがわかります。
とても物を置ける状態ではなく、僕が上に乗ると簡単に穴が開きました。
特に痛みが激しい所は床がめくれて釘も浮いてしまっています。

via
diy-magazine.jp
まずは床を解体していきます。
これだけ傷んでいるので、引っ張るだけで簡単に剥がすことができました。
床を剥ぎ終わると壁際に巾木(はばき)があるので一緒に取り外します。
上から釘止めされているだけなので、バールで引き抜くと外れました。
これだけ傷んでいるので、引っ張るだけで簡単に剥がすことができました。
床を剥ぎ終わると壁際に巾木(はばき)があるので一緒に取り外します。
上から釘止めされているだけなので、バールで引き抜くと外れました。

via
diy-magazine.jp
次は根太の処理です。
釘をバールで抜き取り、抜けない釘はサンダーで削り落とすかカナヅチで打ち込んでしまいます。
最終的に床板を置いた時に引っかかりが無い状態であればOKです。
釘をバールで抜き取り、抜けない釘はサンダーで削り落とすかカナヅチで打ち込んでしまいます。
最終的に床板を置いた時に引っかかりが無い状態であればOKです。

via
diy-magazine.jp
処理が終わった押入れ床の状態です。
床の張替えは慣れたもので、ここまでの作業で1時間半しか掛かりませんでした。
あとは部屋の高さに合う板を選んではめるだけです。
床の張替えは慣れたもので、ここまでの作業で1時間半しか掛かりませんでした。
あとは部屋の高さに合う板を選んではめるだけです。

via
diy-magazine.jp
押し入れの床板は5.5mmのベニヤ板を使って張替えました。
部屋の床が24mmあるのに、押入れは5.5mmで平気かと不安はありましたが、元々付いていた板も5.5mmだったので、よしとしましょう。
※物を置くことを前提としているのである程度薄い板でも大丈夫という判断です
ベニヤ板をそのまま置ければ楽な作業ですが、綺麗な長方形ではないのでやはり壁際は大変でした・・・。
少しだけ台形になっていたので、角をカッターで削って微調整しながらベニヤ板をはめています。
根太の位置で釘を打ち込み、壁際は巾木を用意して角の隙間を隠すように釘止めしています。
部屋の床が24mmあるのに、押入れは5.5mmで平気かと不安はありましたが、元々付いていた板も5.5mmだったので、よしとしましょう。
※物を置くことを前提としているのである程度薄い板でも大丈夫という判断です
ベニヤ板をそのまま置ければ楽な作業ですが、綺麗な長方形ではないのでやはり壁際は大変でした・・・。
少しだけ台形になっていたので、角をカッターで削って微調整しながらベニヤ板をはめています。
根太の位置で釘を打ち込み、壁際は巾木を用意して角の隙間を隠すように釘止めしています。
押入れを解体して床の張替え完了

via
diy-magazine.jp
傷んでいた板が張り替えられ、かなり綺麗になりました。
たったこれだけですが、見違えますよね。
右側の押入れはクローゼットとして活用する予定です。多少床の強度に不安はあるので、白い化粧板を重ね張りして補強しようと思っています。
※今の状態で床に乗っても大丈夫でした。
押入れの解体は簡単にできると思っていましたが、まさかの備え付けタイプで焦りました。
リビングの備え付け棚を解体した経験が無かったら、断念していたかもしれないです。
たったこれだけですが、見違えますよね。
右側の押入れはクローゼットとして活用する予定です。多少床の強度に不安はあるので、白い化粧板を重ね張りして補強しようと思っています。
※今の状態で床に乗っても大丈夫でした。
押入れの解体は簡単にできると思っていましたが、まさかの備え付けタイプで焦りました。
リビングの備え付け棚を解体した経験が無かったら、断念していたかもしれないです。
次回は、天井の穴を塞ぐ作業と砂壁にベニヤ板を取り付ける作業です。
和室と洋室の壁を壊して部屋を繋げた際に天井に穴が空いたので、その部分を塞ぎます。
天井裏に入って一部補強材を入れたりします。
和室の砂壁をどうやって隠すか悩みましたが、コストと時間を考えてベニヤ板を使う事にしました。
その辺りの悩み、苦戦したポイントなども一緒にお伝えできればと思います。
タグに「セーチのリノベ記録 一軒目」とつけていくので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。なるべく工程別に解説できるように、シリーズ物としてお伝えしていきます。
※この記事は2019年1月29日に「DIY MAGAZINE」で公開された記事を再編集したものです。
和室と洋室の壁を壊して部屋を繋げた際に天井に穴が空いたので、その部分を塞ぎます。
天井裏に入って一部補強材を入れたりします。
和室の砂壁をどうやって隠すか悩みましたが、コストと時間を考えてベニヤ板を使う事にしました。
その辺りの悩み、苦戦したポイントなども一緒にお伝えできればと思います。
タグに「セーチのリノベ記録 一軒目」とつけていくので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。なるべく工程別に解説できるように、シリーズ物としてお伝えしていきます。
※この記事は2019年1月29日に「DIY MAGAZINE」で公開された記事を再編集したものです。






