
目次
28歳で福岡へ移住し、築40年の物件をセルフリノベーションしながら生活。その様子をブログメディア「DIY MAGAZINE」で公開しているセーチです。2軒目3軒目に続いて、築50年の戸建て(4軒目)をリノベーションしてきた過程をお届けします。
セーチのリノベ記録 4軒目
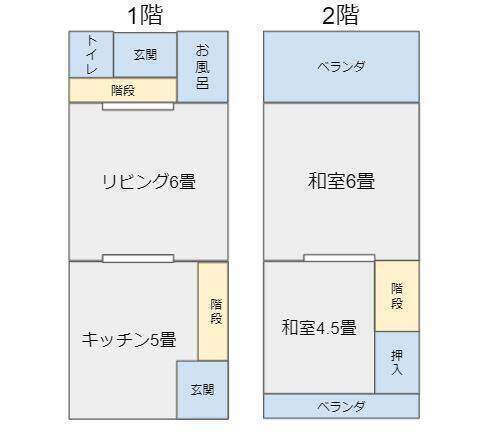
via
diy-magazine.jp
祖父母の物件をセルフリノベーションしつつ、インテリアなどを作っているセーチです。
今までのDIY経験を活かして、関西の築50年空き家をセルフリノベーションして住むことにしました。
古い家のリノベーションを検討している方、築古の家がどんな風に変わっていくのか気になる方の参考になるよう、シリーズでお伝えしていきます。
今回は壁と床とキッチンを撤去する作業です。
今までのDIY経験を活かして、関西の築50年空き家をセルフリノベーションして住むことにしました。
古い家のリノベーションを検討している方、築古の家がどんな風に変わっていくのか気になる方の参考になるよう、シリーズでお伝えしていきます。
今回は壁と床とキッチンを撤去する作業です。
前回の記事はこちら
壁の状態確認から

via
diy-magazine.jp
天気の良い日中でも奥の和室はどんより。
流石に暗いなと思い、リビングに光が入るようキッチンとの間にある壁を解体することにしました。
キッチン窓や玄関からは光が差し込むので、この壁が無くなれば奥の部屋まで光が差し込み、区切られた部屋も広く使えて雰囲気がだいぶ変わると思います。
壁の造りを確認してみると、キッチン側はベニヤ板が施工され和室側は砂壁の上に壁紙が貼ってある状態でした。キッチン側の壁は押すと凹むくらい薄い板なので簡単に剥がせそうです。
流石に暗いなと思い、リビングに光が入るようキッチンとの間にある壁を解体することにしました。
キッチン窓や玄関からは光が差し込むので、この壁が無くなれば奥の部屋まで光が差し込み、区切られた部屋も広く使えて雰囲気がだいぶ変わると思います。
壁の造りを確認してみると、キッチン側はベニヤ板が施工され和室側は砂壁の上に壁紙が貼ってある状態でした。キッチン側の壁は押すと凹むくらい薄い板なので簡単に剥がせそうです。
配線や棚を撤去する

via
diy-magazine.jp
壁を解体する前にコンセントを外しておきます。※電気工事士の資格が必要です。
普通であれば壁の中に配線を隠しますが、このくらいの築年数になると配線はだいたいむき出しで壁や柱にステップルという金具で固定されています。
この家もむき出しの配線。
キッチン側から柱に沿って和室のコンセントに繋がっていました。
ガス、水道、お風呂関係の業者に見積もりを出してもらっている最中で、電気配線も合わせてやってもらえるか確認した所、やはり天井を剥がさないと難しいとのこと。今回は天井を剥がさずに進めたいと思ってたので残念です。
※分電盤だけ交換してもらい、増設するコンセントは壁の裏を這わせようと思います。
普通であれば壁の中に配線を隠しますが、このくらいの築年数になると配線はだいたいむき出しで壁や柱にステップルという金具で固定されています。
この家もむき出しの配線。
キッチン側から柱に沿って和室のコンセントに繋がっていました。
ガス、水道、お風呂関係の業者に見積もりを出してもらっている最中で、電気配線も合わせてやってもらえるか確認した所、やはり天井を剥がさないと難しいとのこと。今回は天井を剥がさずに進めたいと思ってたので残念です。
※分電盤だけ交換してもらい、増設するコンセントは壁の裏を這わせようと思います。

via
diy-magazine.jp
砂壁の中を確認してみると竹に砂を固めているタイプでした。
竹が交差上に編み込まれ、その上に土が固められています。
砂壁にも種類があり、ボードの下地に砂が固められている物が多いですが、古い家だと竹に土を固めている所もあります。ここはまさに竹と土を使った砂壁です。
竹が交差上に編み込まれ、その上に土が固められています。
砂壁にも種類があり、ボードの下地に砂が固められている物が多いですが、古い家だと竹に土を固めている所もあります。ここはまさに竹と土を使った砂壁です。

via
diy-magazine.jp
先に表側の砂壁をバールの先で削るように落とします。(塊で落ちていきます)
※ボード状の砂壁であれば叩くと簡単に割れますが、竹がしなってなかなか崩れません。
※ボード状の砂壁であれば叩くと簡単に割れますが、竹がしなってなかなか崩れません。

via
diy-magazine.jp
表側の砂を削ったら、裏側から竹の間にバールを刺して残りの砂を落とします。
土台の竹は3.4ヵ所頑丈でしたが、それ以外はペラペラで土を乗せる受けとして編み込まれたようです。
竹同士は紐で結ばれているだけなので、引っ張ると簡単に外せました。
土台の竹は3.4ヵ所頑丈でしたが、それ以外はペラペラで土を乗せる受けとして編み込まれたようです。
竹同士は紐で結ばれているだけなので、引っ張ると簡単に外せました。

via
diy-magazine.jp
上段の砂壁も同じように取り除いたら、ベニヤ板を固定していた胴縁を解体します。
両端に釘止めされているだけなので、真中に切れ目を入れて上下に動かせば簡単に引き抜けました。
両端に釘止めされているだけなので、真中に切れ目を入れて上下に動かせば簡単に引き抜けました。

via
diy-magazine.jp
鴨居も撤去しこれで頭をぶつけることもなさそうです。
壁が無くなったことで、キッチンと玄関からの光が和室まで差し込むようになりました。
後は廃材を土嚢袋に詰めてまとめておきます。
※ここまでの作業を動画にまとめています。
壁が無くなったことで、キッチンと玄関からの光が和室まで差し込むようになりました。
後は廃材を土嚢袋に詰めてまとめておきます。
※ここまでの作業を動画にまとめています。
粉塵が舞うのでゴーグルは必須ですね。
ライフラインの見積もりが来るまでに、できる箇所からどんどん進めたいと思います。
ライフラインの見積もりが来るまでに、できる箇所からどんどん進めたいと思います。
キッチンのクッションフロア剥がし

via
diy-magazine.jp
キッチンには薄緑色のクッションフロアが貼られています。
※クッションフロアの下はフロアタイルが貼られてました。
コンパネの繋ぎ目が見えれば解体しやすくなるので、とりあえずクッションフロアは全面剥がし、廃棄が楽にできるよう小さくカットし袋にまとめておきます。
※クッションフロアの下はフロアタイルが貼られてました。
コンパネの繋ぎ目が見えれば解体しやすくなるので、とりあえずクッションフロアは全面剥がし、廃棄が楽にできるよう小さくカットし袋にまとめておきます。

via
diy-magazine.jp
床下点検口はビス止めされているので外して、スクレーパーを差し込んで持ち上げます。
(点検口の入り口を開けて持ち上げた方が簡単です。)
(点検口の入り口を開けて持ち上げた方が簡単です。)
キッチンを撤去する

via
diy-magazine.jp
今回のキッチンは壁にコーキング付けされているだけだったので、引っ張れば簡単に外すことができました。※流し台は、排水トラップの根本にマイナスドライバーを当ててカナヅチで何回か叩いて緩めると外せます。
コンロと流し台は別々なので1つずつ解体しています。
コンロと流し台は別々なので1つずつ解体しています。

via
diy-magazine.jp
完成イメージを膨らませたいので、廃棄する流し台を置いて完成後の雰囲気をチェック。
新しくキッチンを付ける場所を決めあぐねていましたが、玄関横の壁のサイズに合わせて、右側の壁に200㎝くらいのキッチンを新調しようと思います。
玄関側の壁には家電を置く棚や冷蔵庫を設置しようと思います。
新しくキッチンを付ける場所を決めあぐねていましたが、玄関横の壁のサイズに合わせて、右側の壁に200㎝くらいのキッチンを新調しようと思います。
玄関側の壁には家電を置く棚や冷蔵庫を設置しようと思います。
探り探り床を解体

via
diy-magazine.jp
床を剥ぎたいのですが、根太がどこにあるか分からないので、端の傷んでいる所から解体します。
めくっていくと、「厚さ12mm・幅300mm」の板に薄いベニヤ板を重ね張りしている作りでした。
めくっていくと、「厚さ12mm・幅300mm」の板に薄いベニヤ板を重ね張りしている作りでした。

via
diy-magazine.jp
床板は、あわよくば再利用しようと考えていましたが、こんなに打つかというくらい釘が打ち込まれていて使い物にならないので全部廃棄します。
板の隙間から根太の位置が見えたので、丸ノコで傷つけないよう切れ目を入れて剥ぎました。
※ここまでの作業を動画にまとめています。
板の隙間から根太の位置が見えたので、丸ノコで傷つけないよう切れ目を入れて剥ぎました。
※ここまでの作業を動画にまとめています。
丸ノコで切れ目を入れてはバールを力いっぱい持ち上げて剥がす。
玄関から和室に行く道だけ残して残りは全部解体しました。
床の撤去作業はかなり力がいるので、何回やっても大変です・・・
玄関から和室に行く道だけ残して残りは全部解体しました。
床の撤去作業はかなり力がいるので、何回やっても大変です・・・
次回の作業は、ガス管のチェックをしてもらい、お風呂の解体作業まで進めたいと思ってます。
床を剥いだ状態でないと配管や排水管の位置を確認できないので、業者が来るまでになんとか間に合いました。自分でも配管や排水管がどうやって繋がっているか確認しておきます。
これから古い家のリノベーションを検討している方、築古の家を検討している人の参考になるようなシリーズ。タグに「セーチのリノベ記録 四軒目」とつけているので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。ぜひ参考にしてくださいね。
床を剥いだ状態でないと配管や排水管の位置を確認できないので、業者が来るまでになんとか間に合いました。自分でも配管や排水管がどうやって繋がっているか確認しておきます。
これから古い家のリノベーションを検討している方、築古の家を検討している人の参考になるようなシリーズ。タグに「セーチのリノベ記録 四軒目」とつけているので、順を追って読めばリノベが完成するような構成です。ぜひ参考にしてくださいね。






