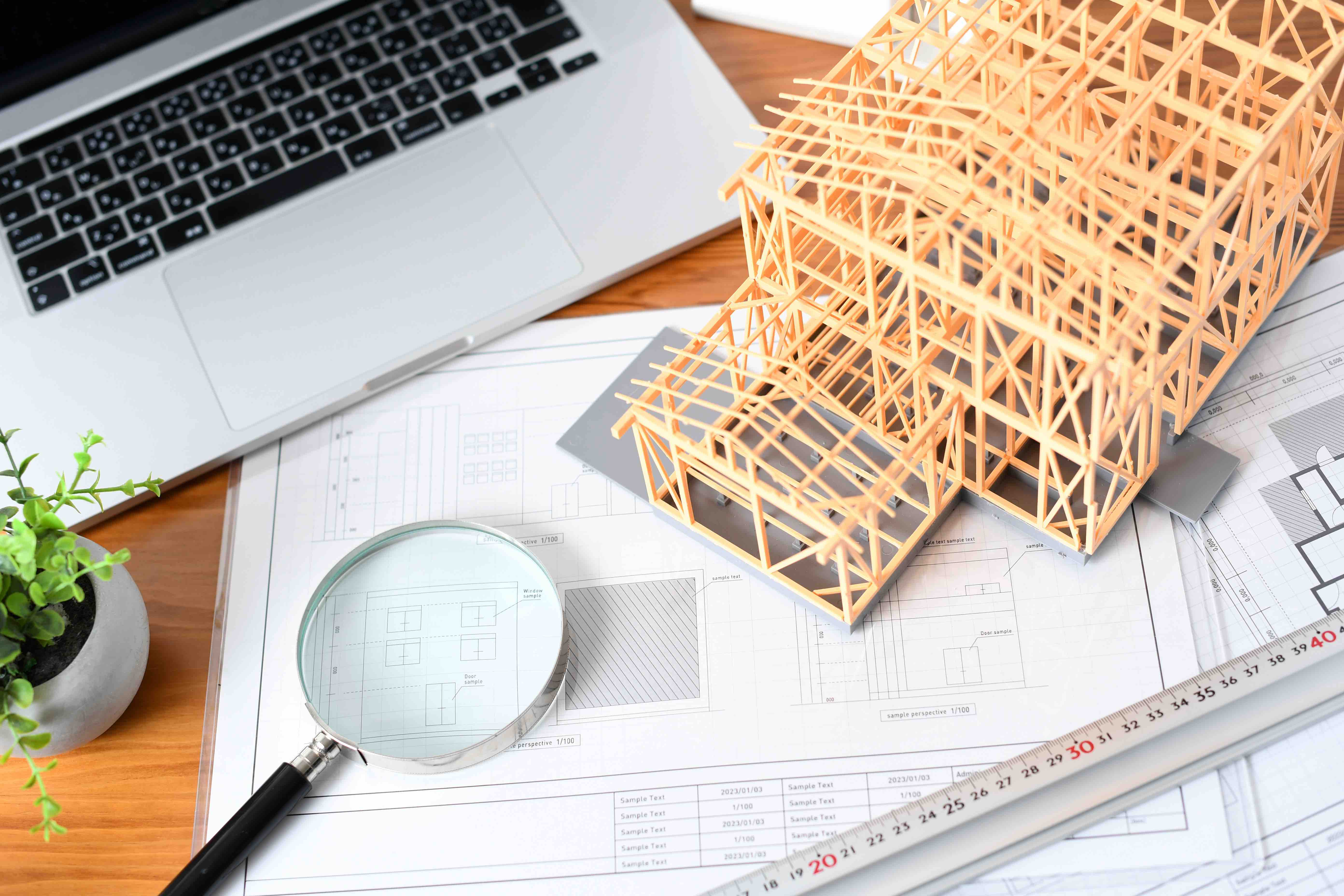
近年、地震などの災害に備えて自宅の強度を見直す人が増えています。特に築年数の古い木造住宅では耐震性に不安があるケースも多く、現在の耐震基準を満たしていない住宅も少なくありません。このような背景から、本記事では耐震リフォームの種類や費用相場、工事の期間や仮住まいの必要性、そして補助金・助成金や減税制度など、リフォーム前に知っておきたい情報をわかりやすく紹介します。
耐震リフォームが必要な住宅の特徴

1981年以前に建てられた住宅
1981年に建築基準法が改正され、耐震に関する基準が強化されました。これは、一定規模の地震が発生しても建物が大きな損傷を受けないようにするための最低基準です。これ以前に建てられた住宅は旧耐震基準で設計されているため、耐震性が不足している可能性があります。一方、2000年以降に建てられた住宅は地盤調査が義務化され、一定の耐震性能が確保されているとされています。
軟弱な地盤に建てられている
住宅の耐震性は、建物自体の構造だけでなく、その下にある地盤の強さにも大きく左右されます。地盤が柔らかいと、地震時に揺れが増幅されやすく、建物の倒壊リスクが高まります。このような土地では、基礎部分をより強化するなど、一般的な建物以上の耐震対策が必要になります。
1階に壁や柱が少ない構造
1階部分に大きな窓や吹き抜けを設けている住宅は、壁の面積が少なくなり、構造上の耐力が低下する可能性があります。その結果、地震の際に1階部分が崩れる危険が高まります。また、1階が店舗やガレージとして使われている場合も、柱が少ないため耐震性に注意が必要です。
基礎部分に損傷がある
建物の基礎にひび割れがあると、耐震性に影響を及ぼすことがあります。幅0.3mm未満、深さ4mm未満の細いひびであれば、大きな問題は生じにくいとされています。しかし、それより大きなひびがある場合は、構造的な安全性に関わる可能性があるため、注意が必要です。
2階部分が張り出している住宅
2階が1階より外側に張り出している造りの家では、上階の重量を1階で十分に支えられず、構造的に不安定になります。地震発生時にバランスを崩しやすく、倒壊のリスクが高くなります。見た目とは裏腹に、1階の壁の上に2階の壁が乗っていない構造は、建物全体の安定性を損なう原因となります。
シロアリの被害がある住宅
土台や柱などがシロアリによって損傷を受けると、建物の構造が弱くなり、耐震性が著しく低下します。特に被害が進行している場合、地震時に建物が倒壊するリスクが高まります。阪神淡路大震災では、シロアリ被害を受けた住宅の多くが半壊または全壊したと報告されています。一方で、被害のなかった住宅は全壊率が約2割、軽微な被害で済んだものが半数以上とされています。
耐震リフォームの流れ

プロによる耐震診断
耐震リフォームは、以下の手順で進められるのが一般的です。まずは、建物の耐震性を専門家が調べる「耐震診断」から始まります。現在の状態でどれほど地震に耐えられるのか、また補強が必要かどうかを判断するための重要なステップです。診断の結果、補強が必要と判断された場合は、次に「補強設計」と「費用の見積もり」が行われます。この設計に基づいて工事の内容が決まり、見積もりを確認したうえで契約を結びます。契約後は、実際の「補強工事」が始まります。建物の状況に応じて、壁や柱、基礎の補強などが行われます。工事が完了した後は、「アフターフォロー」として定期点検やメンテナンスが行われる場合もあります。長期的に安全を維持するために、この段階も重要です。
支援制度の確認
耐震診断やリフォームに対しては、自治体が補助金を出しているケースもあります。支援を受けられるかどうか、事前に地域の窓口や依頼する業者に確認しておくとよいでしょう。さらに、国の支援制度として「所得税の控除」や「固定資産税の減額」といった税制優遇も設けられています。これらの制度についても、併せて確認しておくと費用負担を軽減できます。
耐震リフォームの種類

基礎の補強
建物の基礎は、地盤と建物本体を直接つなぎ、建物全体を支える非常に重要な構造部分です。地震による揺れの力を受け止め、建物の安定性を保つ役割を担っているため、耐震リフォームにおいてはまず基礎の状態をしっかり確認し、必要に応じて適切な補強を行うことが求められます。
補強の方法としては、基礎にひび割れや亀裂が見られる場合に、樹脂や繊維を注入して亀裂を充填し、強度を回復させる方法があります。また、古い建物に多い無筋コンクリート基礎(鉄筋が入っていない基礎)では、鉄筋を含んだモルタルや金属プレートを組み込んだモルタルを重ねることで補強する方法が一般的です。
さらに、基礎が劣化している場合や構造的に不十分と判断された場合には、建物を一時的にジャッキアップし、既存の基礎の上に新しい基礎を構築したり、必要に応じて全面的に基礎を作り直すといった大がかりな工事が行われることもあります。
あわせて、基礎周辺の環境も重要です。床下に換気設備が設けられていない場合には、湿気がこもって木部を腐食させたり、シロアリの被害を引き起こす可能性が高まります。そのため、防湿シートを敷いたり、換気口の増設、さらには防蟻処理を施すことで、基礎とつながる柱や土台部分の長期的な健全性を保つ工夫が行われます。
壁の増設・補強
耐震性能を高めるうえで欠かせないのが、建物に加わる力を受け止める「耐力壁」の強化です。地震時には建物に縦方向の荷重(建物の重さ)と、横方向の力(揺れや風圧)が加わります。これらの力を適切に分散し、建物全体の変形や倒壊を防ぐのが耐力壁の役割です。
特に木造住宅では、壁の配置や構造が耐震性に大きく影響します。開口部が多く壁の少ない家や、建築当初から筋交いが設置されていない壁面では、地震時の変形や倒壊リスクが高まります。耐震リフォームでは、こうした弱点を補うために以下のような対策が行われます。
- ・耐力壁の増設
建物内部に新たに壁を追加する方法や、大きな窓を縮小して壁面積を確保する方法があります。また、外壁工事や増築工事とあわせて、外部から耐力壁を増やすことも可能です。耐震性と同時に断熱性能や遮音性能も向上するケースがあります。 - ・既存の壁の補強
既存の壁に斜め方向の「筋交い」を設置して補強する方法が代表的です。さらに、構造用合板や耐震用パネルを貼り付けて壁の剛性を高める方法、金属製の補強金物を取り付けて壁と柱の接合部を強化する方法などもあります。
これらの補強は建物全体のバランスを考慮して配置されるため、専門家の設計と計算に基づいたリフォームが不可欠です。
接合部の補強
木造住宅では、柱・梁・筋交いなどの構造材が「仕口(しくち)」や「継手(つぎて)」と呼ばれる工法で接合されています。これらは、木材同士を組み合わせる伝統的な技術ですが、耐震性という観点では十分とはいえない場合があります。
近年の新築住宅では、こうした接合部を「耐震金物」で補強し、構造体を強固に固定することが標準となっています。しかし、築年数の古い住宅では金物が使用されていないケースが多く、地震の揺れによって接合部分が外れたり、破損したりするリスクがあります。
耐震リフォームでは、こうした接合部に金物を後付けすることで、柱や梁、筋交いなどの構造材同士をしっかりと固定し、一体化させます。この補強により、建物全体が連動して揺れに抵抗する構造となり、部分的な崩壊を防ぐことができます。
屋根の軽量化
屋根の重さも建物の耐震性に大きく影響する要素です。屋根が重いと建物の重心が高くなり、地震時には揺れの影響を強く受けてしまいます。そのため、屋根が重たい建物ほど、倒壊や損傷のリスクが高くなる傾向があります。
特に、日本の古い住宅では伝統的な瓦屋根が使われていることが多く、このような屋根は耐久性に優れる一方で非常に重いため、耐震性の観点では不利となります。実際に過去の地震では、瓦屋根の重さが原因で建物が倒壊した例も少なくありません。
耐震リフォームでは、こうした屋根の葺き替えによって軽量化を図る方法が取られます。具体的には、通常の瓦から軽量瓦への変更、化粧スレートと呼ばれる薄型の屋根材や、耐久性と軽量性を兼ね備えたガルバリウム鋼板などの金属屋根への葺き替えが一般的です。
屋根を軽くすることで、建物の揺れを抑えるだけでなく、構造全体にかかる負荷も軽減され、他の耐震補強との相乗効果が期待できます。また、軽量化によってリフォーム後のメンテナンスがしやすくなるというメリットもあります。
家族の安全を守る耐震リフォームは、カシワバラにお任せください!
いつ起こるか予測できない地震に備えることは、安心して暮らすために欠かせません。大切な家族や住まいを守るために、誰もができる限りの対策をしておきたいと考えるのは自然なことです。万全の耐震対策で大切なご家族を地震から守りましょう。不明点がある場合や、どんな事例があるのかを知りたい場合は、カシワバラ・コーポレーションまでお気軽にご相談ください。お客様に最適なプランをご提案いたします。






